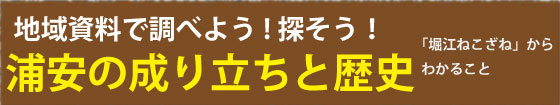
地域資料で調べよう!さがそう 浦安の成り立ちと歴史 〜「堀江ねこざね」からわかること
1889(明治22)年4月、当代島村、猫実村、堀江村の3村が合併して、浦安村になりましたが、浦安になる以前は、どのような地域だったのか、「地域資料」で調べてみましょう!
「地域資料」とは、浦安の歴史や文化などについて書かれた資料(図書や地図など)で、町や市が編纂した「浦安町誌」や「浦安市史」、地元の方が著された昔話などがあります。このページでは、この「地域資料」を用いて、浦安”以前”について、調べてみます。また、地域資料だけでなく、一般の所蔵資料や国立公文書館がインターネットで公開している古地図も活用しました。
*地域資料は、中央図書館レファレンス室で所蔵しています。分館でも一部所蔵しています。
| 浦安市立図書館の所蔵資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資料名 | 著者 | 出版事項 | 刊行年 | |
| 地域資料 | ||||
| 浦安町誌 上 | 浦安町誌編纂委員会 | 浦安町役場 | 1969年 | |
| 浦安の歩み | 浦安町誌編纂委員会 | 浦安町役場 | 1975年 | |
| 浦安 文化財めぐり | 浦安市教育委員会生涯学習課/編 | 浦安市教育委員会 | 2001年 | |
| 浦安市史 まちづくり編 | 浦安市市史編さん委員会 | 浦安市 | 平成11年 | |
| 浦安市史 生活編 | 浦安市市史編さん委員会 | 浦安市 | 平成11年 | |
| 浦安物語 | 宮崎長蔵 | 飯塚書房 | 昭和55年 | |
| 市川市史 第一巻 | 市川市史編纂委員会/編 | 市川市 | 昭和49年 | |
| 詳細 行徳歴史年表 | 鈴木和明 | 文芸社 | 2018年 | |
| 日本古代史地名事典 | 加藤謙吉、他/編 | 雄山閣 | 平成19年 | |
| 隅田川をめぐる文化と産業 浮世絵と写真でみる江戸・東京 |
たばこと塩の博物館/編 | たばこと塩の博物館 | 2016年 | |
| 一般資料 | ||||
| 幕末明治大地図帳 | 清水靖夫/監修 | 平凡社 | 2021年 | |
| 江戸近郊道しるべ | 村尾嘉陵/著 阿部孝嗣/訳 |
講談社 | 2013年 | |
| 江戸百景今昔 | 大野光政 | 本の泉社 | 2009年 | |
| 広重TOKYO 名所江戸百景 | 小池満紀子、他 | 講談社 | 2017年 | |
| インターネット公開データ | 外部リンク | |||
| 国立公文書館デジタルアーカイブ『葛西筋御場絵図』 | 『葛西筋御場絵図』 (アクセス:2022年7月13日) |
|||
| 国立国会図書館 NDLイメージバンク 『「堀江ねこざね」名所江戸百景』 |
『「堀江ねこざね」名所江戸百景』 (アクセス:2022年7月13日) |
|||
まず最初に、『浦安町誌 上』を見てみましょう。p.3の「本町の変遷」に、“保元2年(1157年)には既に部落が形成されて”ましたが、”人口は少なく、塩を焼き、魚介類をとるかたわら、田畑を耕し、生業としていた”とあります。また、豊受神社について、“豊受大神を祀り、保元2年(1157年)の創建といわれる。”とあります。保元2年は、今から、約870年前の平安時代後期、平氏が台頭してきた頃です。町誌には、これ以前については、記録や言い伝えがないためか、記載がありません。
そこで、お隣の市川市の歴史について書かれた、『市川市史 第一巻』を見てみます。第一巻の副書名は、「原始・古代」で、行徳地域の地質なども詳しく書かれています。p.46に、”江戸川の河口では、海岸線が大きく南に突出している。この江戸川左岸に沿っては、江戸川放水路が江戸川から分岐する大和田付近から稲荷木-下新宿-本行徳-伊勢宿-欠真間-新井にかけての行徳街道沿いに、幅200〜300m、高度2〜3mの微高地が発達する。これに対比できるものは江戸川右岸の東京都江戸川区の小岩-篠崎-今井間にもみられる。これらの微高地はその分布、形態からみて、明らかに江戸川の作った自然堤防である。”、”行徳から浦安にかけての地帯では、江戸川と東京湾のほぼ中間に、土地利用の差によってわずかに認められる微高地として連続する。この高まりは、海岸の砂が磯波の作用によって打ち上げられた浜堤である。”とあり、江戸川と東京湾にはさまれ、砂が堆積したような地質であることがわかります。
『詳細 行徳歴史年表』p.33には、”白雉元(650)年に、下総国府が国府台(市川市)に置かれる。行徳はまだ海の底か、葦や萱が生い茂る湿地帯だった”とあり、浦安も、同様であったと考えられます。そして、この当時、浦安と行徳、そして現在の東京都江戸川区の葛西あたりは、下総国葛飾郡に属していました。
次に、この下総国について調べるために、『角川日本地名大辞典 12 千葉県』を見てみましょう。p440の「しもうさのくに 下総国」に、”下総国は、大化年代(西暦645〜650年)に統一され、現在の千葉県北部・茨城県南部・埼玉県西部・東京東部を含む”とあります。浦安と葛西がひとつの国であったことからわかるように、この当時は、江戸川が国境ではありませんでした。
では、江戸川が国境になるまでは、下総国と武蔵国の国境は、どこだったのでしょうか?
『日本古代史地名事典』p.242の「下総国 しもうさのくに」に、”西は利根川、隅田川を境として武蔵国と接し”とあり、現在の都県境(江戸川)よりも、西寄りでした。
ところで、江戸川は、江戸時代以前は、何と呼ばれていたのでしょう。もう一度、『角川日本地名大辞典 12 千葉県』でp.161の「えどがわ 江戸川」を見ますと、”古くは渡良瀬川(わたらせがわ)の下流で太日河(ふといがわ)と呼ばれていた”とあり、『更級日記』や『万葉集注釈』にも、「ふといがわ」の名が見られるようです。
『浦安町誌 上』p.5に、前述の保元2年(1157年)から100年ほど後、”とくに永仁の大津波には、多数の神社、仏閣、民家などが流失し、村はいっこうに発達しなかった”とあります。海抜が低かったからでしょう、当代島にあった十戸は、全て流されてしまったと言い伝えられています。
この津波は、正応6年(西暦1293年)4月に発生した鎌倉周辺を震源とする大地震(鎌倉大地震、永仁関東地震)が引き起こした災害でした。
そして、この永仁の津波で大きな被害が出たため、部落の人々は、”豊受神社付近に堅固な堤防を築き、その上に松の木を植え、津波の襲来に備えた。”、”この松の根を波浪が越さじとの意味から「根越さね」といい、それがいつの間にか猫実と称されるようになった”とあります。
浦安では、このような水害に、幾度も見舞われ、人々は離散集合を繰り返したようです。
それから、約250年後、『浦安町誌 上』p.4の「堀江村」には、“足利氏の末世弘治年間*に津波のため漂没するところとなり、村民は住居を江戸に移し、堀江町(現中央区堀江町)に居住し、小網町を網乾場に使用するようになった。”とあり、またしても大きな水害にあいました。*弘治年間は、西暦1555〜1558年
この堀江町は、現在でもあるのでしょうか?新しい地図で探しても、見つかりませんでしたが、『幕末明治大地図帳』で探したところ、p.105や110で中央区堀江町が見つかりました。現在の地図で同じ場所を調べてみると、小網町に近い中央区日本橋小舟町辺りであることがわかりました。
さらに古い地図を国立公文書館デジタルアーカイブで「重要文化財 国絵図等」から探したところ、『江戸近郊御場絵図』の『葛西筋御場絵図』などが見つかりました。
住民が堀江町に移住してから、60年ほど経った頃、『浦安物語』p.176によると、1620(元和6)年、田中内匠と狩野浄天という人が、徳川幕府に許可を受けて、現在の鎌ヶ谷市囃水付近から行徳を通り、当代島の船圦川(現在は、船圦緑道)まで、用水路を堀りました。この用水路は、「内匠堀(たくみぼり)」と呼ばれ、長い間、排水路、灌漑用水路として、人々の暮らしを支え、使われていました。この用水路は、『葛西筋御場絵図』*(下記にリンクあり)で見ることができます。
そして、この頃、武蔵国と下総国の国境が江戸川になりました。『浦安町誌 上』p.4に、”猫実村は徳川幕府の直轄地となった。”と、あります。江戸近郊に設定された幕府の御鷹場の一部だったようです。前述の『葛西筋御場絵図』に堀江、猫実、當代島などの地名がみえます。また、江戸川の上流、「柴又」のあたりに、「江戸川中央武蔵国下総国国境」の文字が読めます。
*国立公文書館デジタルアーカイブ:『江戸近郊御場絵図』-『葛西筋御場絵図』[外部リンク]
当館の所蔵資料で『江戸近郊御場絵図』に関するものがあるかキーワード「江戸近郊御場絵図」で検索したところ、残念ながら一冊もヒットしませんでした。そこで、キーワードを「江戸近郊」に変更して、検索したところ、『江戸近郊道しるべ 現代語訳』などがヒット。この資料を確認してみると、1834(天保5)年に清水徳川家の御広敷用人、村尾嘉陵によって書かれた現代語訳で、p.222に収録されている「真間の道芝」に、市川へ行くために、江戸から行徳までを船を使った日帰り旅行の様子が書かれていました。そこには、“東郊の葛飾や真間の辺りへ行こうと、くづれ橋(箱崎橋、中央区日本橋小網町と日本橋箱崎町との間に架かる橋)の手前にある行徳舟の舟出所(日本橋小網町の行徳河岸)を指して行く”とあります。前述の、堀江町にもほど近い場所です。当時、浦安・行徳一帯は、海産物と塩の重要な産地として江戸との間を水運でつないでいましたが、それだけでなく、人々の移住による結びつきが数百年に渡り、あったのかもしれません。
なお、行程は、午前6時頃、現在の中央区九段2丁目の自宅を出て、午前10時頃、行徳に着いたとあります。実に、片道4時間におよびました。九段から小網町まで、徒歩で約1時間かかります。舟の待合に20分かかるとすると、舟にのっているのは、2時間半位でしょうか。この頃のルートは、日本橋の行徳河岸から小名木川、新川、江戸川を通り、行徳へ向かうルートで、『隅田川をめぐる文化と産業』p.38やp.46にわかりやすく書かれています。
『江戸近郊道しるべ』が刊行された約20年後、浮世絵師、歌川(安藤)広重が、1856(安政3)年から1858(安政5)年にかけて、制作した『名所江戸百景』に「堀江ねこざね」(「堀江、根古ざね」)があり、当時の情景を垣間見ることができますので、見てみましょう。
名所江戸百景.png)
国立国会図書館「NDLイメージバンク」の「名所江戸百景」 [外部リンク]
『堀江ねこざね』では、左奥に富士山が見えますので、東から西に向かって描かれています。全体的に、ヨシ(葦)と思われる植物が茂り、手前の砂浜のような場所では、猟師が鳥を狩猟(鴨猟?)しているように見えます。また、土手の高さから、海抜が非常に低いことがわかります。
中央を右上から左下に流れる境川と思われる川に2つの橋が架かっています。手前の橋は、境橋でしょうか。『浦安町誌 上』p.151の「境橋」に、”この橋は、本町で一番最初に東学寺前に架けられた橋で、堀江村と猫実村をを結ぶ唯一の橋として、天保年間(1830〜1843年)に架設されたものである。”、”古くは、“東堺橋”といった。”とあります。このため、境橋は、「堀江ねこざね」が描かれる約20年ほど前に架けられた計算になり、前述の『江戸近郊道しるべ』が刊行された頃と考えられます。
この境橋と思われる橋近くの、分岐点から手前側は、江間川と呼ばれていました。これが江間川なら、この分岐点あたりが現在の大三角線が通る江川橋あたりになります。そして、p.153に、“江川橋から3、400メートルぐらい下流のところが、巳の方向(南南東かそれよりやや北)に三分ぐらい曲がっているところから、その付近を巳の三分というようになった。”とあり、角度的に合致してみえます。
猫実村(川の右側)には、松林に囲まれて、鳥居が見えます。境橋より奥まってみえますが、『江戸百景今昔』のp.246や『広重TOKYO 名所江戸百景』のP.226では、これを豊受神社としています。
豊受神社は、明治初年までは神明宮社と呼ばれていました。1805(文化2)年に作られたとされる『葛西筋御場絵図』では、海岸線に近いところに鳥居のマークと“神明”の表記が確認できます。
『浦安町誌 上』には、社殿が、1850(嘉永3)年に、たび重なる風水害により破損したので、現在(1969(昭和44)年当時)の社殿を建築したとしています。
このことから、広重の「堀江ねこざね」は、再築されて間もない頃(6〜8年後?)に描かれた、真新しい社殿ということになり、再築される1973(昭和48)年までは、広重が描いた社殿がそのまま残っていたことになります。
再築については、『浦安 文化財めぐり』p.15を閲覧しました。
この版画は、どこから描かれたものでしょう?境川の角度や境橋の位置を考え合わせると、ひょっとしたら、現在の中央図書館あるいは、東小学校あたりから(当時は遠浅の海)、『浦安市史 生活編』p.38の青ギス釣りの写真に写っているように、脚立に座って描いたのかも、知れませんね。
明治維新の後、『浦安町誌 上』p.3によると、1878(明治11)年に、堀江村、猫実村、当代島村は、千葉県東葛飾郡に属することになりました。この頃、当代島村は、欠真間村と新井村と連合していたとのことで、現在の南行徳区域の一部だったとも言えます。そして、1889(明治22)年4月1日、町村制の施行にともない、堀江、猫実、当代島(欠真間村と新井村との組替地を除く)が合併して、浦安村が誕生しました。
いかがでしたでしょうか?このページでは、地域資料を使って、浦安になる前のことを調べてみました。図書館では、ここで紹介した以外にも、多くの地域資料を所蔵しています。江戸時代の出来事など、さらに詳しく調べるには、『浦安市史 まちづくり編』や『浦安物語』なども、おすすめです。「地域資料」をぜひご活用ください。
地域資料の一部のリストをご覧いただけます→[リンク]